機械警備業務の目的と内容
機械警備とは、防犯カメラやセンサーなどの機械装置を用いて施設や資産の監視を行い、人間による従来の巡回とは異なる効率的かつ効果的な警備方式です。人と機械の役割を使い分けることで、広範囲の監視や夜間の見逃し防止などが可能になり、コスト削減やセキュリティ強化にも貢献します。さらに、機密情報や出入口の監視においては、機械警備が精度の高い監視手段として有効で、犯罪の抑止にもつながります。これらの特性により、近年、機械警備と有人警備を組み合わせたハイブリッドなセキュリティ体制の導入が進んでいます。
機械警備業務管理者とは?資格とその要件
「機械警備業務管理者」とは、都道府県の公安委員会より「機械警備業務管理者資格者証」の交付を受けた者で、機械警備業務の適正かつ効果的な運用を担える高度な専門知識と業務管理能力を有する者と認められた人を指します。警備業法により、機械警備業者は基地局ごとにこの管理者を選任することが義務付けられており、無資格では従事できません。資格取得には都道府県公安委員会主催の講習(3日間)と最終日の終了考査(1日)を受け、80%以上の得点で合格する必要があり、受講料は約39,000円です。実務経験や受講資格に制限はなく、誰でも挑戦可能で、合格率も高いため、適切な準備があれば取得しやすい資格と言えます。
機械警備業務管理者が必要な仕事はどのくらい?
全国でどれくらい機械警備が使われている?
日本では、センサーや防犯カメラを使って建物や施設を見守る「機械警備」を行っている警備会社が全国に約540社あります。
これらの会社が見守っている施設はおよそ340万か所もあり、年々増加しています。スーパーやオフィスビル、工場、学校など、いろんな場所が対象です。
管理者は必ず配置が必要
法律では、機械警備の「基地局」(警備センターのような拠点)ごとに、必ず1人は機械警備業務管理者を置くことが決まっています。
この資格を持った人がいないと、機械警備の仕事はできません。
大きな警備会社では基地局が複数あることもありますが、最近の法律改正で、一定条件(施設が5,000か所以内など)を満たせば、1人が複数の基地局を兼任できるようになりました。
どれくらいの人数が必要?
単純に計算すると、全国で少なくとも540人以上の機械警備業務管理者が必要になります。
実際には大きな会社で兼任する場合もあるため、もう少し少なくて済むこともありますが、それでも数百人規模の資格者が全国で活躍していることになります。
この資格は未経験からでも挑戦でき、講習を受けて試験に合格すれば取得可能なため、需要は高めです。

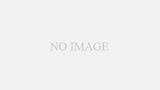
コメント