1.雇用形態と法律の違い:守衛と警備員、それぞれの立場
守衛と警備員は仕事内容では施設の巡回や受付など施設警備の業務を行いますが、雇用主が異なる点がまず大きな違いです。警備員は警備会社に属し、施設からその会社へ警備を依頼して派遣される形態となります。一方、守衛は施設や土地の管理者が直接雇用し、給与や指示も管理者から受けます。
また、法律(警備業法)の適用にも明確に違いがあり、警備員は法律上の研修義務や制服・持ち物の届け出、欠格事由の適用など厳格に規定されているのに対し、守衛にはこれらの規制が及びません。守衛は管理者の指示に従う形で比較的柔軟に働くことが可能です。
2.研修・規律の違いと制約の有無
警備員には、法律に基づく「新任研修」(20時間以上)や年間「現任研修」(10時間以上)が義務づけられており、継続的な法改正や知識向上への対応が求められます。また、制服や警棒などの持ち物についても公安委員会へ届け出が必要で、厳格なルール下で業務を行う必要があります。
それに対して守衛には法定研修や服装・持ち物の規制がなく、服装や携帯品も自由ですが、組織によっては独自の研修制度を設ける場合もあります。欠格事由(18歳未満、薬物や飲酒問題、過去違反者など)も警備員には適用されますが、守衛には法律上の制限はありません。ただし、実務上雇用前の判断は慎重に行われることが多いです。
3.安定性と求人上の見分け方の難しさ
警備員を派遣する警備会社の主たる事業は「警備業」であり、現在の社会情勢では一定の需要があり安定性も期待できますが、技術革新や警備システムの普及によって将来的な不安もあります。一方、守衛の立場は施設の管理会社やビル所有者の雇用で、警備業は補助事業として位置づけられていることが多く、他事業が安定していれば守衛の仕事も安定する可能性がありますが、過度な期待は禁物です。
さらに求人情報では「守衛」と明記されていても、実際には警備会社から派遣される施設警備員としての働き方が多く、求人文言だけで厳密に区別するのは難しいのが現状です。業務内容は同じでも、形態的には警備員であるケースがほとんどです。

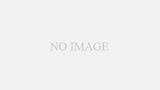
コメント