警備業と警備員の役割と分類
警備業は、依頼者からの契約に基づき、施設や人々の安全を守る業務を行う事業者を指します。一方、警備員は、その警備業者の下で実際に警備業務を遂行する従業員を指します。警備業務は以下の4つに分類されます:
- 第一号警備:商業施設や工場などの施設を警備する業務。
- 第二号警備:工事現場やイベント会場での交通整理や人の誘導を行う業務。
- 第三号警備:現金や貴重品の運搬および警護を行う業務。
- 第四号警備:要人の身辺警護、いわゆるボディーガード業務。
警備業者と警備員の欠格要件
警備業法第3条には、警備業者や警備員として従事できない欠格要件が定められています。主な要件は以下の通りです:
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者:破産が決定すると、復権を得るまで警備業に従事できません。
- 禁錮以上の刑や警備業法違反で罰金刑を受け、処分から5年を経過していない者:刑務所から出所後、5年間は警備業務に就けません。
- 直近5年間で警備業法に違反した者:重大な違反と認定されれば、5年間の業界追放となります。
- 暴力団員と関わりがある者:暴力団との関係がある場合、警備業務への従事は認められません。
- アルコールや薬物の中毒者:中毒者は業務の適正な遂行が困難と判断されます。
- 心身に障害を抱え、業務を適正に行うのが難しい者:医師の判断により、業務遂行が困難とされる場合があります。
- 営業許可が下りない未成年者:2022年の民法改正により、18歳以上が成年とされ、警備業務に従事可能となりました。
2019年の警備業法改正とその影響
2019年に警備業法第3条第1項が改正され、「成年被後見人及び被保佐人」という文言が削除されました。これにより、成年後見人や被保佐人とされる方々も、警備業者や警備員として従事することが可能となりました。この改正は、差別や人権侵害を防ぐ観点から行われ、より多くの人々が警備業に関わる道を開くものとなっています。

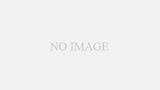
コメント