安全靴の基本と必要性
警備員には、安全靴を使うというイメージがありますが、そもそも安全靴とは何かをまず知ることが重要です。安全靴とは、日本工業規格(JIS)に基づき、つま先が強化樹脂や鋼鉄でガードされ、滑り止め機能が備わっている靴のことです。警備員向けの靴にも多様な商品がありますが、安全靴と呼ぶためにはJIS規格を満たさなければなりません。また、すべての警備業務で安全靴が必須というわけではありません。例えば交通誘導警備や工場警備など危険性の高い現場では、安全靴の使用が望ましい一方、ショッピングモールでの巡回警備のように危険性が低い場合は、安全靴が不要な場合もあります。
安全靴の種類と付加機能
では、具体的にどんな安全靴を選ぶべきか、種類と性能に注目しましょう。まず安全靴には、以下のような種類があります:
- 短靴:くるぶしより下の丈の靴
- 中編上靴:くるぶしより少し上まで覆う靴
- 長編上靴:すねの下あたりまで覆う長めの靴
さらに、さまざまな付加機能を持つタイプも存在します。例えば、甲プロテクタ付きで足の甲を衝撃から守るタイプ、耐踏抜き機能があり鋭利なものを踏んでも貫通しないもの、そして長時間の立ち仕事に対応するため、かかと部に衝撃エネルギー吸収機能がある安全靴などです。これらの機能により、業務特性に応じて最適な靴を選ぶことができるといえます。
安全靴を選ぶ際のポイント
実際に安全靴を選ぶ際には、まず勤務先の会社に確認することが大切です。会社が使用する安全靴を指定している場合もあります。自分で用意する場合には、次のポイントを抑えましょう。
- JISマークの有無:安全靴である証明として必須です。
- サイズの適合性:店舗で実際に履いてみて、軽く動いてみることが重要。足に合わないサイズは靴ずれや動きづらさにつながり、怪我の原因にもなります。
- 季節や時間帯による機能選び:たとえば真冬の屋外作業にはボア付きのあたたかい靴、夜間業務には反射板付きで視認性の高い靴が適しています。
以上のように、業務内容や環境、自分の体に合った機能を見極めて安全靴を選ぶことが、安全かつ快適な警備業務に繋がります。

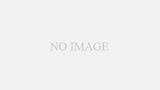
コメント