1. 自家警備とは何か?制度の基本的な概要
自家警備とは、工事現場などで必要な交通誘導警備を、専門の警備会社に委託するのではなく、建設会社などの発注者自身が自社の社員により対応する形態のことを指します。本来、交通誘導は国家資格や専門教育を受けた警備員が担うものですが、昨今の深刻な警備員不足を背景に、やむを得ない場合に限り自家警備の導入が許可されるようになりました。特に地方や災害復旧現場など、人手確保が困難な地域では、従来の外注型警備に代わる現実的な選択肢として注目を集めています。
この制度は一時的な特例措置としてスタートしたものではありますが、慢性的な人材不足の現状を考慮すると、今後さらに制度の整備や導入が進む可能性があります。交通誘導警備の外注コストが高騰する中、コスト面でも自家警備の魅力は大きいと言えるでしょう。
2. 制度化の背景と国の通達
自家警備が公に認められるようになったきっかけは、2017年6月に発出された総務省・国土交通省の連名通達「交通誘導員の円滑な確保について」です。この通達では、特に災害復旧工事のように緊急性が高く、かつ交通誘導員の確保が困難なケースに限り、発注者自身による交通誘導を「例外的に可能」とする方針が打ち出されました。
また、地方自治体においても柔軟な対応を促すよう求められ、実際に自治体ごとに認められる範囲や条件が異なるケースも見られます。たとえば、比較的交通量の少ない地方の市道では自家警備が認められている一方で、交通量が多く事故リスクが高い国道や幹線道路では、引き続き専門の警備員による対応が求められる傾向にあります。
3. 自家警備導入に必要な条件と資格要件
自家警備を導入するには、いくつかの厳格な条件をクリアする必要があります。まず大前提として、「警備員を確保できない正当な理由」が求められます。これは単なるコスト削減目的では認められず、例えば複数の警備会社に依頼をしたが全て断られた、地域に警備会社が存在しないなど、証明できる根拠が必要です。
さらに、自家警備を担当する自社社員についても、交通誘導に関する基礎的な講習(例えば安全教育や道路交通法の理解など)を受講させることが推奨されており、場合によっては「交通誘導警備業務検定2級」などの資格保有が求められることもあります。加えて、現場に応じた交通量や工事の規模に適した体制づくり、安全対策マニュアルの整備なども重要なポイントとなります。
4. 自家警備のメリットと導入による効果
自家警備の大きなメリットは、何よりもコストの削減です。警備会社に委託する場合、1人1日あたり1万5千円〜2万円程度の費用が発生しますが、自社社員による対応であれば外注費を大幅に抑えることが可能です。特に工事期間が長期にわたる場合や複数人の警備が必要なケースでは、その差は数十万円から数百万円に及ぶこともあります。
また、警備会社のスケジュール調整や人材手配の手間が不要となり、工程管理がしやすくなるという点も魅力です。急なスケジュール変更にも社内で柔軟に対応できるため、工期遅延を防ぐことにもつながります。さらに、現場作業員が交通状況や現場の特性を熟知しているため、より的確な誘導が可能となり、安全面でもメリットがあると評価されています。
5. 注意点と今後の展望
一方で、自家警備の実施にあたっては慎重さも求められます。まず、自治体によっては一切認めていない地域もあるため、事前に各自治体の方針を確認する必要があります。また、自社社員による交通誘導中に事故が発生した場合、警備業法の枠外であるにもかかわらず、責任の所在が曖昧になるリスクもあります。適切な保険加入や責任区分の整理も必須となります。
今後、自家警備制度のさらなる明確化と安全管理体制の強化が求められる中で、企業には法令遵守を前提とした計画的な導入と、社員教育の充実が不可欠です。警備員不足という社会的課題の解決に向けて、自家警備は一つの選択肢として定着していく可能性がありますが、そのためには業界全体の共通認識と制度的なバックアップがより一層求められるでしょう。


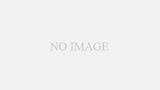
コメント